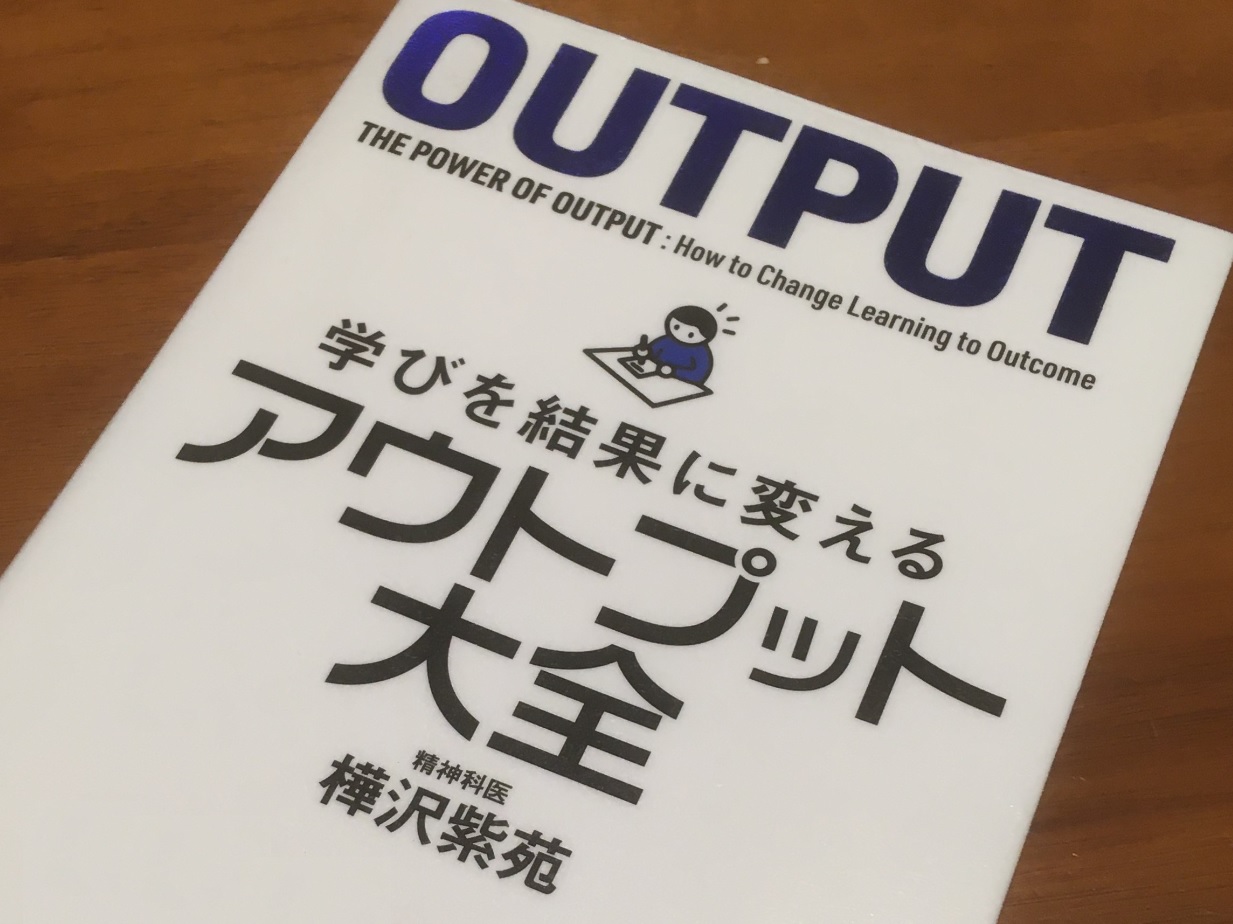『学びを結果に変えるアウトプット大全![]() 』
』
著者:樺沢 紫苑 / 出版:サンクチュアリ出版
自分の今の状況に対し、改善したいがどうすればよいのかわからず悩んでいる人や、自分をさらに成長させたいと思う人におすすめの本です。
「アウトプット」という言葉はよく耳にしますが、実際の「アウトプット」とのギャップはないか、自分自身を見直すいい機会を与えてくれました。アウトプットをいっぱい出したいと思わせてくれる本です。
今回の本はこちら → 「アウトプット大全」
関連記事はこちら → 「【ビジネス】インプット大全」
アウトプットとは
「アウトプット」とは何でしょうか。成果、出来高、目に見える物…
この本では、「インプット」「アウトプット」を以下のように定義しています。
インプット:脳の中に情報を入れること、「入力」すること
アウトプット:脳の中に入ってきた情報を脳の中で処理をし、外界に「出力」すること
具体的には、「読む」「聞く」がインプットで、「話す」「書く」「行動する」がアウトプット と表現しています。
目の前の現実を変えたいなら、どんどん話そう、書こう、行動しよう
インプットすることで情報や知識は増えますが、増えただけでなにも仕事をしていません。自己満足であればそれでもいいかもしれませんが、現実的には何も変化が起きていないのです。アウトプットは「行動」することで現実の世界に影響を与えます。
得た知識をアウトプットすることで「自己満足」から「自己成長」へとつながります。
樺沢さんは、得た知識をアウトプットして、「わかったつもり」を卒業しようと指摘しています。

よく学んだことをより深く理解するには、人に説明すると良い と聞きますが、まさにそれですね。私もアウトプットを心掛けようと思います!
「話す」アウトプット
自分の言葉で、自分が体験したことを、飾らずに伝えよう
アウトプットの重要性と自己成長へのつながりは理解できましたが、具体的にどうアウトプットすればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
その答えとしては、「昨日の出来事を友人に話すことも立派なアウトプット」と紹介されています。
この行動により、脳が活性化し、記憶が増強され、定着にも大きく貢献します。
感想を話すときのコツは「自分の意見」「自分の気づき」をひとつでも盛り込むことです。
この本の中で、話す言葉の注意点も挙げられています。
ポジティブな言葉を増やすことで幸せになれる
成功したければ、ポジティブな言葉で自分の周りを満たそう
この注意点、非常に重要と考えます。人は忙しくなり余裕がなくなると、悪口や愚痴が圧倒的に多くなってしまいます。ネガティブな言葉が多い人は、仕事も人生もうまくいかない傾向があるとの実験結果があるようです。
そのため、ポジティブなアウトプットを増やさない限り、成功や幸せにはつながらないとのことです。

ポジティブな会話をするのが重要だとわかった。
会話の具体的なシーンで注意すべきことはあるだろうか?
会社において、上司と部下の関係があります。そのなかでの会話において「ほめる」「叱る」も重要はアウトプットとなります。
「ほめる」「叱る」について、苦手意識を持っている方は多いと思いますが、「ほめる」「叱る」は、アウトプットでありフィードバックでもあります。樺沢さんは、「ほめる」「叱る」によって「気付き」が誘発され、「自己成長」が引き起こされると述べています。
自己成長を促す「ほめ方」「叱り方」は以下のように紹介されていますので、実行できるように意識したいです。
①「強化したい行動」をほめる
②具体的にほめる 強化したい「具体的な行動」をできるだけ細かくほめる
③承認欲求を満たす 人から承認される、認められる欲求
④文章でほめる 本人が読み返すことができる、読み直すたびに「ほめ」効果
①怒らない、感情をぶつけない
②「修正」したい具体的行動を指摘する(「行動の変化」を促す)
③フィードバックする(失敗した原因、今後の対策を一緒に考える)
④「叱る」「叱られる」~信頼関係を築く
「書く」アウトプット
いっぱい書く、ノートに手書きで、絵やイラスト図をいれながら
ひらめきがほしければ、問題を徹底的に考えた後、ぼーっとしてアイデアを待つ
学校で勉強していたとき、先生から「書いて覚えよう!」とよく言われていたかと思います。漢字や英単語を覚えるときに、ノートにびっしり書いていたのを思い出しました。「書く」という行為によって、脳のポテンシャルが最大限に引き出される研究結果があるようです。本を「読む」ときも書き込みをすることで、本の内容理解度が圧倒的に深まると述べられています。

具体的に仕事を想定した際、書くことによるメリットはなにがあるのだろう?
仕事量が多く、漫然とやることに追われる毎日となってしまう人は多いのではないでしょうか。時間内に集中的に行うには、「TO DO リストを朝1で作成する」が良いと紹介されています。
管理人も毎日朝、その日に行うタスクを時間割にしています。朝1は最も集中率の高い時間帯だそうで私もこの時間はかなり重要視しています。一日の成果がここで決まるといっても過言ではありません。
この本にも、「TO DO リストは1日の仕事の設計図」と言われています。1日の仕事の流れが頭の中でイメージできると、それが「成功イメージ」のイメージトレーニングをしているからです。
また、アイデア発想においても「書く」アウトプットは重要です。「ひらめく」には、必死に脳を働かせるイメージがありますが、実はリラックスした時間を持つことが意外にも重要であるようです。
リラックス時に降りてきたひらめきを、逃すことないように普段からいつでも「書く」ことができるようにアウトプットする必要があります。
実現したい目標は胸に秘めるのではなく、どんどん口にしよう
目標を明言、提示することで、緊張感が高まり実際に目標達成に向けて大きく後押ししてくれます。

私は、納期にあわせて事前報告日を決めて、上司や関係者との会議設定します。
すると「やらなきゃ!」という責任感と少しの緊張感が生じますね。
その感覚と同じだ。
「行動」アウトプット
行動を「楽しい」と思えると、自然と長く「自己成長」を続けられる
やっぱり成長するには「行動」が必要です。
なかなか「行動」するには面倒になったり、億劫になったりするかと思いますが、「続ける」ことが重要だと述べられています。
ビジネスにおける究極の成功法則のひとつ挙げるとしたら、それは「続ける」ことです。
とにかく、続けないと結果は出ません。
樺沢さんは、以下のことを毎日続けているようです。
・メルマガ 毎日発行 13年
・Facebook 毎日更新 8年
・Youtube 毎日更新 5年
・加圧トレーニング(毎週) 8年
・月1回のまったく新しい内容でのセミナー開催 9年連続
・年2冊以上の出版 10年連続

いやいや、超人じゃないですか!本当にやってるの?って疑いたくなるほど。
一般人でもできるのかな?どうやっているのか覗いてみたい…
この本には、「続ける」ことが非常に得意な樺沢さんの極意が紹介されています。
①「今日やる」ことだけを考える
②楽しみながら実行する
③目標を細分化する
④結果を記録する
⑤結果が出たらご褒美をあげる
チャレンジなくして自己成長はなし
本当にその通りと考えます。
チャレンジのレベルを上手にコントロールすることで、学習意欲が沸き、集中力が高まり、やる気も高まり、記憶力も高まり…と自己成長が楽しいと感じるかと思います。
チャレンジレベルの設定ですが、「ちょっとがんばればなんとかなりそう」レベルが良いようです。
その「ちょい難」の課題チャレンジを繰り返すことで、結果として大きな課題をクリアすることができます。
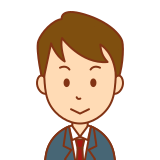
なかなか仕事が始められない。億劫になるんだよね。
やる気がでるまで待ちたいな…
わかります。その気持ち。管理人もそうです。
やる気があるときに、仕事をしたいと誰もが思いますが、現実はそうではありません。いつまでたってもやる気が出てこないときはあります。
ここで、まず始めることが重要です。もうしょうがない、やるしかないのです。
最近の脳科学でも、まず始めることで5分経つと「やる気スイッチ」がオンになるとの結果があるようです。まずはダメ元でも5分、やり始めるとやる気はあとからついてきます。
まとめ
アウトプットすることの重要性が良くわかる良書でした。
この本を読んで、管理人も眠っているインプットをたたき起こして、色々なことにチャレンジするアウトプット=自己成長したい!と強く思いました。
皆さんも一緒にアウトプットする生活をしてみたらどうでしょうか。
今回の本はこちら → 「アウトプット大全」